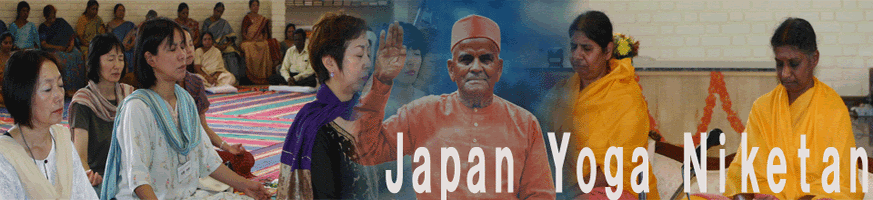「老人とヨーガ」 木村慧心
1,ヨーガ行者の長寿
私たちヨーガを行じる者の間では、老化にまつわる話は時として多く語られてきています。それらは「眉唾もの」の話とお聞き下さっても結構ですが、弟子は年を重ねるのに師匠の方は数十年来昔のままの姿形を保っている、などという話は、インドの各地で語り継がれています。
私のヨーガの師匠スワミ・ヨーゲシヴァラナンダ大師様も、1985年4月に99歳でお亡くなりになられましたが、生前から、自分はヒマラヤのふもとに下りて弟子を教え導くというエネルギーを消耗する役を果たしてきたので百歳までは生きない、とおっしゃられていました。その御言葉の通りに、99歳で、一週間の間に続けて3回起こされた心臓発作の後にお亡くなりになられましたが、98歳になられる時までに、ご自分の墓となるであろう瞑想ホールを完成されていました。
そのホールが完成された時に、独り言のように「私が死んだら皆がうろたえるだろうな」とおっしゃられていたそうですが、翌年にその御言葉どおりに他界されました。 後に兄弟弟子たちに私が聞いた話では、心臓の拍動が止まったにもかかわらず、師匠の肉体は冷たくなるどころか、熱くなり続けたそうです。さらには死後硬直も起きずに柔らかい体のままでしたので、翌日に葬儀のために集められたバラモン僧たちは師匠の遺体に触れて、「このお方は本当に亡くなられているのか?」と騒いだそうです。それで仕方なく、町から氷を買ってきて師匠の遺体を冷やしておいてから、地下の遺体安置所にご遺体を納められたということです。
こうした通常では見られない事々をヨーガ行者たちは見せてくれるので、ヨーガの修行自体が心身に何か不可思議な変化を生じさせることは、古く3000年ほど前にウパニシャッド聖典が書かれ始めた時には、すでに聖典の中に、「ヨーガを行じる者は老化や死を克服する」という文言として記録されるようになっていました。
ちなみに私の師匠のそのまた師匠であるアートマナンダ大師というお方は、私の師匠がヒマラヤ山中の聖地ガンゴートリ手前に流れているシャムガンガ上流にある洞窟内でお会いした時は「何歳であるか分からぬほどのお方だった」と、私の師匠はおっしゃられていました。このアートマナンダ大師は、常日頃はヒマラヤを越えたチベット高原のカイラス山近くにある修行場、ティルタプリにお住まいでした。このティルタプリは、チベット潜行で有名な大阪は堺の仏教僧、河口慧海も、「この霊場を訪れなければカイラス巡礼もその甲斐がない」と紹介しているほどに、行者たちには知られた霊場なのですが、私が今から12年前にカイラス山巡礼の後にこの地を訪れた時には、行者たちの住まいした数百はあるであろう小さな洞窟群には、一人のヨーガ行者の姿も認めることが出来ませんでした。私の先々代の師匠はこの地で数百年を生きたらしいのです。しかしもとより戸籍も出生証明書もないヨーガ行者の話ですから、この長寿の話を全くの眉唾ものと見なされても結構ですが、しかし私たち弟子は、先々代の師匠の長寿はあり得ることであると考えているのです。
2,人間の体は内燃機関である
3000年も前のヨーガの教典、ウパニシャッド聖典によれば、人間の体は5つの層に分類できる体になっていると理解されています。その一番外側の肉体は「食物鞘(アンナマヤ・コーシャ)」と呼ばれており、この体がすり切れてきた時は、口から入れる種々の食物の成分によって補ってやればよい、とされています。先の長寿に関する肉体の話も、ヨーガ行者のこの食物鞘の部分の話なわけです。なぜ、ヨーガ行者の食物鞘は丈夫で長持ちするのでしょうか? それは、行者たちの住む場所と食べ物に関係しているのです。
私の師匠や先々代の師匠の住んでいた場所はヒマラヤ山中であり、チベット高原でした。下界と比べてこれらの場所の特徴は、酸素が少ないということです。 さらにこれらヨーガ行者たちの食べ物はきわめて粗食でした。私の師匠は、ヨーガ行者ですから全くの菜食で、高タンパク、高カロリーの肉や卵類は一切口にされませんでした。また、先々代のアートマナンダ大師にいたっては、口にされるのは高原に生える草の根を火にあぶったものだけだったそうです。
差し出された砂糖菓子は、「自分はそういうものは食べない」と言われたそうです。これらの事を総合して考えてみれば、少ない燃料を少ない酸素でトロトロ燃やす図式が考えられます。 例えば、私たちが冬に使う鋳物製のダルマ・ストーブを思い浮かべてください。燃料の薪をドンドン入れて、焚き口から勢いよく酸素を吹き込んでやれば、薪は激しく燃えて熱いエネルギーをそこに発生させるでしょうが、この鋳物製のストーブはひと冬でひび割れて使いものにならなくなってしまうかも知れません。反対に、少しの薪をトロトロとゆっくり燃やすようにしてこのストーブを使えば、半永久的に使い続けられるかも知れません。
食物鞘(アンナマヤ・コーシャ)と昔からインドで呼ばれてきている私たちの肉体も、体の活動に必要な最小限の燃料たる食べ物を補給しつつ、その燃料を燃やす酸素も少しずつ体内に取り入れるだけにしていれば、あるいは信じられないほどの永さにわたって食物鞘を使い続けられるかも知れないのです。この仮定の話を現実に実行してきているのが、ヒマラヤ山中に住まいし続けてきたヨーガ行者たちだったのです。
例えば先に紹介した私の先々代の師匠の食事内容と、チベット高原という酸素の少ない居住環境を考え合わせてみれば、この仮定の長寿条件にぴったりと当てはまることははっきりしています。 ちなみに、日本における最長寿県が沖縄と長野県であること、またアメリカの長寿州の一位は沖縄と同じく太平洋上のハワイであり、その次に続くのがロッキー山脈沿いの州であることも山岳地帯の長野県の長寿の例と符合しています。酸素の多寡を考えると、ハワイや沖縄は海抜0?bに近いわけですから、なぜに長寿条件を満たしているかと疑問に思われる方々もいるかと思いますが、これらの島は亜熱帯気候で、熱せられた水蒸気から生じる低気圧が原因して降雨日が多いことはよく知られています。ということは、こうした島々は気圧の低い状況によくおかれているわけですから、山岳地帯同様に酸素の量が少ないと言えるわけです。その他気候が温暖であるとかいろいろな条件はあるにしても、ダルマ・ストーブに例えた私たちの肉体たる食物鞘を長持ちさせる条件の一つである酸素量の少なさは、ハワイも沖縄も十分に満たしていると言えるのです。
3,ゆっくりと火を燃やすためのカルマ・ヨーガ実習
長寿の条件に関して見落としてはならない心理的要因があります。それは、エネルギーを消耗させる心の動機に関してです。ダルマ・ストーブは多量の薪と酸素で耐用年限を減じさせられますが、人間の場合は自分の肉体にどれほどの燃料(血中の糖分)と血中酸素を供給するかは、自分で決定しています。例えばインスリン非依存型糖尿病患者の場合には、自分の体内から造り出すインスリン量では対応できかねるほど多量の血糖を増加させています。
血糖自体は戦うための燃料ですから、糖尿病患者は「戦わない。ゆったりと生きてゆく」と決意しさえすれば、異常な血糖値の高まりを生じさせなくても済むはずなのです。こうした決意を促して初めて、この型の糖尿病はその病因を取り除けるはずであるというのが、ヨーガ・セラピーの考え方です。
ヨーガの一部門にカルマ・ヨーガというヨーガ実習法がありますが、この種のヨーガでは私たちの行為に関する智慧の数々を学べるようになっています。こうした行為に関する智慧は何もインドだけで発見されているわけではなくて、例えば我が国においても、「捕らぬ狸の皮算用」「後悔先に立たず」「過ぎたるは及ばざるがごとし」等々、多くの先人たちの、行為に関する言葉が今でも生きた教えとして語り継がれています。さらには、隣国の中国からも、「人間万事、塞翁が馬」という格言が、行為の結果に対する身の処し方を教えてくれています。
インドのカルマ・ヨーガでも、こうした格言で教えられている行為に関する智慧とほぼ同様な教えが、守るべきものとして語り継がれています。詳しくはカルマ・ヨーガの教典、バガヴァッド・ギーターをひもといていただければよいと思いますが、要は自分に与えられた責務を自分の能力一杯にきちんとやり遂げ、その行為から生じてくる結果は全て絶対者ブラーフマン(あるいは神仏)からの贈り物としてありがたくいただく精神に徹して生きる生き方が、推奨されています。 こうした精神のもとで、燃料と酸素の量を調整しつつ、ヒマラヤ山中のヨーガ行者の如くの長寿を全うしたいものです。
本稿は、紙面の都合から詳しい科学的データーは割愛しましたが、先般東京で開かれた第22回日本アーユルヴェーダ学会に招聘したインド国防省付属国防研究所所長のセルヴァムルティ先生らは、本稿とも関連するようなヨーガの生理学的研究報告をされていることを最後に記して、ヨーガと老化の項を終わらせていただきます。